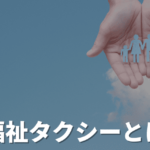「介護タクシーって何?」
「介護タクシーの使い方(利用方法)を知りたい」
このような方に向けて、本記事では「介護タクシーとは?利用方法や料金、使い方の流れ」を徹底解説していきます。
介護タクシーとは

介護タクシーとは、要介護状態の方や体の不自由な方が外出する際に利用できる、便利なサービスです。
一般のタクシーと同じように利用者を目的地まで移送するだけでなく、乗降時には介護資格を保有する運転手による介助を受けることができます。
また、料金の一部に介護保険を適用できます。
介護タクシーの利用条件や対象者
介護タクシーの利用条件や対象者には、以下のような特定の要件が設定されています。
このサービスは要介護認定を受けている方、つまり介護保険1級から3級の方、要支援1級または2級の方が対象です。
自力での移動や歩行が困難な方、車椅子利用者、ストレッチャー利用者も利用可能です。
さらに、日常生活上または社会生活上必要な外出、例えば通院、買い物、冠婚葬祭への参列などの目的で利用することができます。
これらの条件を満たすことで、必要な場所への移動を安全かつ適切に支援することが可能です。
介護タクシーの利用方法
介護タクシーの利用方法は、基本的には以下になります。
- 介護事業所またはタクシー事業者に予約する
- 利用日時、利用目的、利用者情報などを伝える
- 当日、指定された時間に利用場所に介護タクシーが到着する
- 運転手が介助を行いながら、車に乗降車する
- 目的地に到着後、料金を支払う
介護タクシーの具体的な利用方法は事業所によって異なる場合がありますので、利用前に必ず詳細を確認してください。
事前の確認により、当日の手続きがスムーズに進み、適切なサービスが受けられるようになります。
介護タクシーの料金仕組み
介護タクシーにおける支払い体系は、サービスの種類に応じて異なります。
このサービスは大きく二つのカテゴリに分類されます。
訪問介護サービスとしての対応
こちらは「通院等乗降介助」というカテゴリで介護保険が適用される場合があります。
適用されると、全体の費用の大部分が介護保険でカバーされ、利用者の自己負担は全体の少ない割合に抑えられます。
一方、介護保険の適用外となる場合、各事業所が独自に設定した額が適用されます。
福祉タクシーとしての対応
こちらは介護保険の適用外の場合に利用されることが多く、料金体系は事業所によって設定されます。
通常、一般のタクシーよりもコストが抑えられる傾向にあります。
金額や詳細については、地域の介護保険担当窓口や介護事業所にお問い合わせください。
介護タクシーを利用する流れ

介護タクシーを利用するには、大きく分けて以下の5つのステップがあります。
- 要介護認定を受ける
- ケアプランを作成する
- 介護タクシー事業者を選定・契約する
- 利用内容・乗車予定日を決める
- サービスを利用する
1つずつ解説していきます。
1. 要介護認定を受ける
介護タクシーを利用するためには、まず市区町村に要介護認定の申請を行い、要介護1以上の認定を受ける必要があります。
2. ケアプランを作成する
要介護度が決定したら、担当するケアマネジャーに相談し、ケアプランを作成します。
ケアプランには、介護タクシーの利用に関するサービス内容や利用頻度などが記載されます。
3. 介護タクシー事業者を選定・契約する
ケアプランに基づき、複数の介護タクシー事業者から見積もりを取り、利用する事業者を選定します。
事業者によっては、送迎エリアや料金体系、車両の種類などが異なるので、比較検討することが重要です。
4. 利用内容・乗車予定日を決める
利用する事業者が決まったら、利用内容や乗車予定日などを具体的に決めます。
利用内容は、通院、買い物、リハビリ施設への通いなど、介護保険で認められている範囲内であれば自由に決めることができます。
5. サービスを利用する
乗車予定日になったら、介護タクシー事業者が自宅まで迎えに来てくれます。
利用者は介助を受けながら、安全かつ快適に目的地まで移動することができます。
介護タクシーを探すときのポイント

介護タクシーを探すときのポイントとして、以下の3点を押さえておきましょう。
- ポータルサイトを利用する
- 見積もりをする
- タクシー運転手と相性
1つずつ解説していきます。
ポータルサイトを利用する
まず、介護タクシーを選ぶ際は、ポータルサイトを利用しましょう。
弊サイト「カイタクネット」を利用すれば、自分に合った介護タクシーを選べます。
キーワード検索や都道府県・市町村、業態検索を使えば、誰でも簡単に介護タクシーを利用できるので、ぜひご活用ください。
見積もりをする
介護タクシーを選ぶ際には、事前に複数の事業所から見積もりを取ることが重要です。
見積もりを取ることで、サービスの内容とそれに対するコストを比較検討できます。
見積もりを依頼する際は、必要なサービス(乗降介助、距離、待機時間など)を明確に伝え、それに基づいた全体の費用を把握しましょう。
また、介護保険の適用があるかどうかも確認することで、自己負担額を正確に予測することができ、予算内で最適なサービスを選ぶ手助けになります。
タクシー運転手との相性
介護タクシーの利用では、運転手との相性も非常に重要です。
運転手はただ移動を手助けするだけでなく、乗車時の介助や安全な運転を担保し、場合によっては利用者とのコミュニケーションを取ることも求められます。
事前に事業所に訪問して運転手と直接会うか、電話等で話をすることで、運転手の対応や人柄を確認することが可能となっています。
介護タクシーを安心してサービスを利用するためにも、信頼できる運転手を選ぶことが大切です。
介護タクシーに関するよくある質問
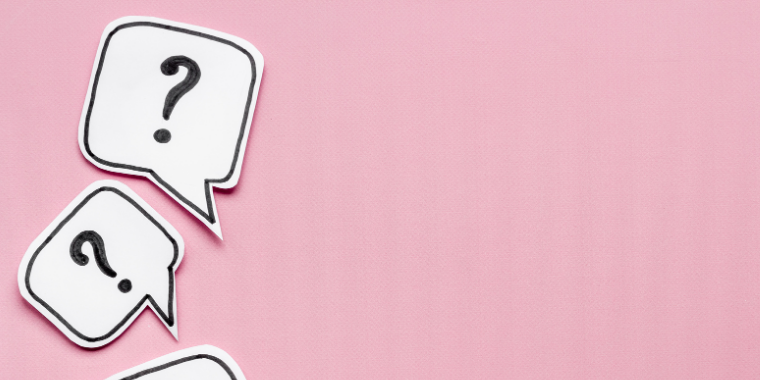
最後に、介護タクシーに関するよくある質問に回答していきます。
- 介護タクシーは保険適用されますか?
- 介護タクシーでは家族同乗できますか?
- 介護タクシーとタクシーの料金の違いはなんですか?
介護タクシーは保険適用されますか?
介護タクシーの保険適用は、利用するサービスの種類によって異なります。
通院や治療のための移動など、介護保険の「通院等乗降介助」に該当する場合、介護保険が適用され、利用者の自己負担は通常1割です。
しかし、全ての介護タクシーサービスがこの保険適用内に入るわけではなく、保険適用外のサービスでは完全自費となります。
介護タクシーでは家族同乗できますか?
介護タクシーでの家族の同乗は、多くの事業所で可能です。
家族が同乗することで、利用者の安心感を高めると同時に、移動時のサポートも手厚くなります。
ただし、車両の大きさや座席数、利用者の安全や快適性を考慮した上での対応となるため、事業所によって異なります。
介護タクシーとタクシーの料金の違いはなんですか?
一般的に介護タクシーは、介助サービスや特別な装備が必要とされるため、一般タクシーよりも高額に設定されていることがあります。
また、介護保険の適用を受けられる場合、自己負担が大幅に軽減されることもあります。
料金や同乗者の有無、サービス内容については、事前に確認することが大切です。
まとめ
ここまでで「介護タクシーとは?利用方法や料金、使い方の流れ」の解説は以上です。
本記事は以上です。
最後までご覧くださりありがとうございました。