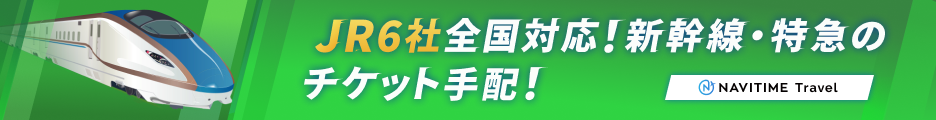「要介護認定がおりてないから、介護タクシーが保険適用にならない。」
「福祉タクシーを使わないと外出できないから仕方ないけど、交通費が心配だ。」
毎回のタクシー利用は交通費がかさんでしまうため、定期的な通院の何割かは自分たちで頑張って送迎している、というご家族も多いのではないでしょうか?
しかし、介護は終わりの見えないマラソンのようなもの。
先の長い介護を乗り切っていくためには、頑張りすぎは禁物です。
とはいえ、タクシー利用は費用がかさむのは事実。
そこで金銭的にも負担を軽くする福祉タクシーの「補助券」の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
これにより自分たちの送迎回数を減らせれば、身体的な負担も軽くすることが出来ます。
当記事では、福祉タクシーで用いることが出来る「補助券」について、紹介したいと思います。
補助券とは
「補助券」とは、一定の基準を満たした障害などを持っている方が、福祉タクシー利用時に使用できる割引券です。
一般的には福祉タクシーだけでなく、保険適用していない介護タクシーでも利用することが出来ます。
ただし、全国一律の制度ではなく、各自治体が交付しているため、そのサービス内容や活用できる条件は異なっています。
名前も「補助券」だけでなく、「利用券」や「タクシー利用券」などと様々です。
当記事では、標準的な内容を紹介いたします。
ご利用の際は必ず、交付元の自治体に確認するようお願いします。

補助券の助成内容
まず標準的な助成内容は下記の通りです。
- 1枚400~700円程度の割引がされる
- 年間50~100枚程度の交付される
- 一度の利用で〇枚まで、と上限が決められている
- 通院回数の多い障害の場合は追加交付(1.5倍程度)もある
補助券1枚当たりの割引は500円前後が一般的。
ですが、多いところと少ないところでは1.5倍程度の差があるようです。
ただし交付枚数も異なっているため、補助額全体でみてみなければ差があるとはいえません。
使用条件でよくあるのが、1回の使用枚数に制限があることです。
多くの自治体は、1回のタクシー代を全額補助券だけで支払うことは出来ないようにしています。
あくまで「補助」という事ですね。
また、人工透析などで通院回数の多い方には追加交付も実施されています。
交付の仕方も様々で、年1回で全ての補助券を交付するところもあれば、月々〇枚で交付するところもあります。
いずれにせよ、平均的な数字で計算すると…
500円×75回=37500円
…となり、年間37500円の補助額となります。
追加交付のある方では、56000円程ほどになるでしょう。

利用できる人
では、この「補助券」はどのような方が利用できるのでしょうか?
基本的には身体障害者手帳や療育手帳を持っている方が、補助券交付の対象になります。
具体的には…
- 1級から3級の身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
…になります。
ですが、手帳をお持ちの方全員が対象ではありません。
さらに「視覚」「上肢」「下枝」「体幹」「移動」「内部機能」などの対象部位が、等級を満たしている必要があります。
つまり、移動が困難な障害をお持ちの方が、補助券交付の対象というわけです。
これに加えて、通院が多い方も交付対象となっています。
自治体によっては、「精神障害」も対象なっていることがあります。
必ず、お住いの自治体に確認するようにしましょう。

補助券を使用する時の注意点
福祉タクシーや介護タクシーの利用を助けてくれる「補助券」ですが、利用には注意が必要です。
代表的なのは以下の4つです。
- 利用は自宅から医療機関への通院のみ
- 補助券は契約事業所でなければ使えない
- 補助券は他の助成と併用して使えない
- おつり、買い取り、他人譲渡は出来ない
1.利用は自宅から医療機関への通院のみ
補助券の利用は、通常「自宅から医療機関への通院のみ」となっています。
つまり買い物など、他の用途には基本的に使えません。
福祉タクシーは買い物や娯楽への送迎を依頼出来たり、家族の同乗が認められていたりと、その自由度が高いのが魅力の一つです。
しかし「補助券」を利用してしまうと、用途が通院のみに限られてしまうので注意が必要です。
また用途が通院であっても注意が必要なケースが存在します。
それは、通っている医療機関が交付した自治体内にあるかどうか。
補助券は自治体単位の制度なので、他自治体にある医療機関は対象外になることがあります。
ですが、利用に関する条件は各自治体によりますので、「通院場所が隣町だ」という方は使用前に確認してみましょう。

2.補助券は契約事業所でなければ使えない
自治体内の医療機関への通院でも、補助券使用の際にはまだ注意が必要です。
それは使用する福祉タクシーの事業所が、自治体と契約しているかどうか。
つまり、補助券は契約事業所でなければ使えないのです。
というのも、福祉タクシー事業者は、利用者から渡された補助券をもって、所定の手続きを行うことでようやく現金に換金されます。
ですが、その手続きも契約業者でなければ、自治体は受け付けてくれません。
不正な届出を防止するためですね。
ですので、福祉タクシー利用者は補助券を使用する前に、事業所に確認しておきましょう。
特にいつものタクシーが予約でいっぱいで、普段使わない事業者を紹介されたときは要注意。
予約時に確認することをお勧めします。
まえもって、自治体ホームページをのぞいてみても良いでしょう。
3.補助券は他の助成と併用して使えない
福祉タクシーの補助券を交付している多くの自治体が、他の助成制度も設けています。
代表的なところでは、公共交通機関である「バス代・鉄道代」に対する助成や、送迎に使用する「自家用車の燃料代」に対する助成、などがあります。
ですが、福祉タクシーの補助券の交付を受けてしまうと、他の助成を申請できなくなります。
つまり「自身の通院方法に適した助成を一つ選んでください。」という行政側からのメッセージですね。
どれを選ぶかはあなた次第ですが、通院方法、費用、身体的負担、家族の負担などを考慮して、選択しましょう。

4.おつり、買い取り、他人譲渡は出来ない
当たり前ですが、補助券は金券ではありません。
福祉タクシーの料金を助成してくれるだけのものです。
ですので、料金以上の補助券を出しても、お釣りは出ませんし、金券ショップに行っても換金は出来ません。
使用条件もあるため、他人に譲渡することも出来ません。
他の助成も検討してみよう
各自治体で行っている「補助券」の助成の他に、別の助成サービスもあります。
- 障がい者割引
- 行政機関以外の割引サービス
1.障がい者割引
この「障がい者割引」は全国で受けられる助成サービスで、なんと「補助券」との併用が可能です。
サービスの使い方も簡単で、対象の障害者手帳などを運転手に提示するだけです。
すると、タクシー料金から1割が引かれるという仕組み。
このサービスの対象となる方は以下の通りです。
- 身体障害者福祉法に基づく「身体障害者手帳」の交付を受けている方
- 療育手帳制度要綱に規定する知的障害者の「療育手帳」の交付を受けている方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方
2.行政機関以外の割引サービス
行政機関が行っている助成の他に、様々な割引サービスがあります。
例えば、LINE登録によるLINEクーポンの発行や、福利厚生サービスに加入している事業所で使えるクーポンもあります。
利用者拡大のため、初回割引券を配布していたり、逆にリピート割引を行っている事業所も存在します。
これらの割引サービスは各事業所のホームページなどで確認できます。
予約の際に問い合わせてみても良いでしょう。

最後に
「補助券」は福祉タクシーを頻繁に利用する方にとって、頼りになる助成制度です。
ですが、自治体単位によって行われており、地域によっては制度自体がない自治体も存在します。
そのような自治体は、代わりに移送サービスを充実させているようです。
各自治体も限られた予算の中、地域の実情に合った助成方法を選択しているのでしょう。
しかし、その分利用者にとって分かり難くなっていることも確か。
当サイトでは分かりやすく利用者様に情報を発信していきたいと考えておりますので、今後もご一読いただければ幸いです。
本記事は以上です。
最後までご覧くださりありがとうございました。