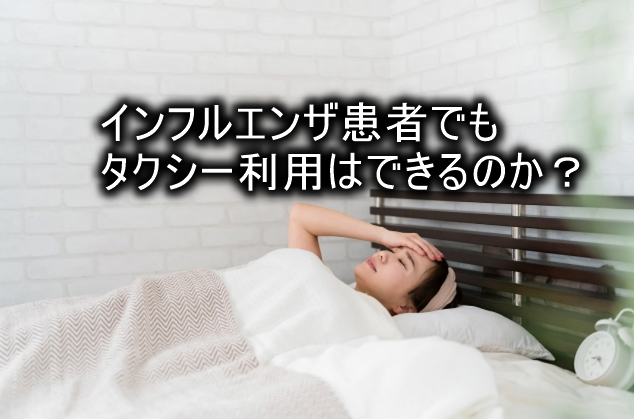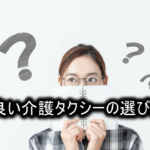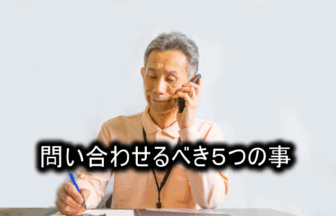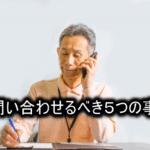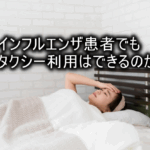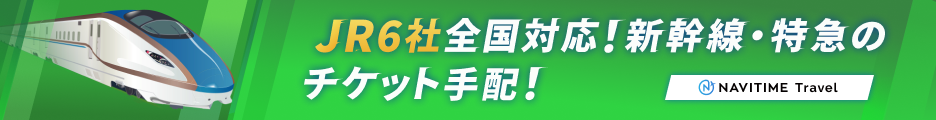発熱してしまった。病院を受診したいんだけど、どうやっていけばいいんだろう?
もしかしたら、インフルエンザかもしれないし…
近年、そう悩まれた方も多いと思います。
コロナ禍以降、発熱に対する社会の対応が変化しつづけているため、現状がわからなくても仕方ありません。
特に自家用車を持っていない方や運転が出来ない方などには、重大な問題になることでしょう。
そのような方の第一の選択肢とあげられるのが「タクシー」です。
そこで当記事では、発熱時のタクシー利用についての現状と、タクシー以外の移動手段について解説したいと思います。
公共交通機関は控えるべき
まず初めに言えるのは「公共交通機関での移動は控えるべき」ということです。
特にバスや電車は不特定多数の乗客が同一空間に乗車します。
そのような空間では、どうしても感染させてしまうリスクが高まるため、乗車は控えましょう。
また、明らかに感冒症状がある方が、自身の隣に座られるといい気持ちはしませんよね。
自分では単なる風邪だと思っていても、周囲の人にはわかりません。
マナー的な観点からも、バスや電車の乗車は自粛すべきです。

発熱時のタクシー利用の現状
公共交通機関の一つである「タクシー」ですが、こちらは少し事情が違います。
というのも、乗り合いでもない限り他の乗客との接触がありません。
そのため、発熱時の移動手段として挙げられやすくなっています。
法律上では、発熱者のタクシー乗車を禁止する規定はありません。
実際に「旅客自動車運送事業運輸規則」で定められているタクシー事業者が乗車を拒否できる条件は、以下の通りです。
- 制止や指示に従わない者
- 危険物などを携帯している者
- 泥酔した者または不潔な服装をした者で、他の客の迷惑になる恐れがある者
- 付添人を伴わない重病者
- 感染症法に定める特定の感染症患者
ここでいう特定の感染症患者とは「一類感染症」「二類感染症」「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」の患者のことです。
要するに、一般的な季節性インフルエンザの患者は乗車拒否の対象ではないのです。
タクシー事業者の発熱者に対する現状
前述したとおり、法的には単なる発熱でタクシー事業者は乗車を拒否することはできません。
しかし、実態としてはタクシー事業者が発熱者の乗車を断るケースが少なくありません。
というのも、事業者側の感染対策はマチマチであり、各事業者の運営スタイルも関係してくるからです。
例えば、運転者と乗客の空間が仕切られ、空気清浄機が完備した感染対策の専用車両を用意している事業所もあれば、感染対策はマスク一つという事業所もあります。
また、仮にドライバーが感染しても代わりのドライバーがいる事業所もあれば、車一台でドライバー1人という個人事業主もいます。
特に個人事業主は感染してしまうと5~7日程度営業できなくなるため、売り上げに直で響きます。
このような個人事業主にとって、発熱者の送迎はデメリットが大きいため、断られるのも仕方がないといったところでしょう。
どうしてもタクシーで行かなければならない場合は、「発熱対応」を掲げている事業所を利用しましょう。
「発熱対応」は各事業所の強みになるので、多くの事業所はホームページなどで宣伝しています。
このような事業所に予約を入れてください。
前もって事情を説明しておくと、スムーズに送迎してもらうことができるでしょう。

発熱時の移動手段
インフルエンザの疑いがあるような場合、バスや電車の利用は感染拡大防止の観点から避けるべきです。
また、タクシーも「発熱対応」を掲げている事業所以外の利用は控えましょう。
では、他にはどのような手段があるのでしょうか?
発熱時の主な移動手段には以下の通りです。
- 徒歩
- 自家用車
- 介護タクシーや福祉タクシー
- 民間救急
1.徒歩
自宅から歩くことが出来る範囲内に病院があるなら、「徒歩」も選択肢の一つです。
しかし高熱の状態で長い時間歩くことは、体力の消耗が激しく、病状を悪化させる原因になりかねません。
そればかりか、病院に向かう途中で倒れてしまう可能性もあるため、推奨は出来ません。
どうしても徒歩を選択する場合は、無理のないように気を付けましょう。
また、病院側が自家用車で待機するよう要請している場合もあるため、徒歩での来院を断ってるかもしれません。
事前に電話で確認しておきましょう。
2.自家用車
運転免許と自家用車を持っている場合は、「自家用車」が最も現実的な選択肢となるでしょう。
他者への感染リスクが最も少ないうえ、徒歩圏外の病院へ向かうことも容易です。
ただし、発熱状態で自身が運転するのは危険な行為です。
高熱や倦怠感などにより、判断力や反射神経が鈍っている可能性があり、事故を起こす確率も高まります。
実際に道路交通法では「病気などの理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転してはならない」と定められています。
そのため、自家用車を用いる場合は、家族や友人にお願いしましょう。
なお、家族や友人に送迎を頼む場合は、感染しないためにも以下の項目に気を付けましょう。
- 発熱者も運転者もマスクを着用する
- 送迎中は2か所以上の窓の上部を少し開けて車内を換気する
- 会話は必要事項以外は控える
- 発熱者は運転者から一番離れた席に座る
- 送迎後は車内を消毒する

3.介護タクシーや福祉タクシー
一般タクシーで送迎を断られた場合、「介護タクシーや福祉タクシー」を利用するもの良いでしょう。
介護タクシーの中にも「発熱対応」を行っている事業者があります。
特に、車いすやストレッチャーでの送迎が必要な場合は有力な選択肢となります。
普段から通院に介護タクシーを使用している方は、まずいつもの介護タクシー事業者に相談してみましょう。
もちろん普段利用しない方も「移動に困難を覚えている方」として、利用することが可能です。
ただし介護タクシーは一般のタクシーと違い、「運賃」のほかに「介護料」の支払いも必要になります。
さらにはオプション代の「発熱対応」の料金もかかってくることを、事前に把握しておきましょう。
4.民間救急
「タクシーでの送迎は断られた。しかし救急車を呼ぶほど重症でもない。」
といった場合は、「民間救急」を検討しましょう。
民間救急は、緊急性の低い傷病者の搬送を行っています。
つまり、インフルエンザ疑いの発熱者を搬送するには最も適していると言えます。
民間救急にはメリットが多くあります。
救急救命士や看護師などの医療に通じたスタッフ同乗すること。
感染対策が施されている専用車であること。
医療器具が搭載されているため、万が一の事態に対し早期対応が可能であること。
またストレッチャーも搭載されているため、横になりながら搬送してもらうことも可能です。
ただし民間救急がある地域も限られています。
自身の居住地域に民間救急の事業者がいるのかどうか、事前に把握しておいても良いでしょう。

まとめ
発熱時にはインフルエンザの疑いがあったとしても、タクシーの利用は可能です。
ただし事業者側の事情から、送迎を断られる場合も少なくありません。
事前にホームページなどで発熱対応可能の事業者を探してから、予約することをお勧めします。
また、タクシー以外でも自家用車や介護タクシー、民間救急などの移動手段もあります。
それぞれの特徴を踏まえて、自身の体調と相談しながら通院方法を検討しましょう。
この記事が、移動に困っている発熱した方の一助となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。