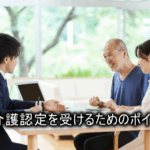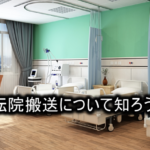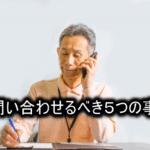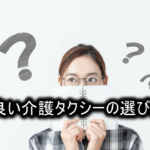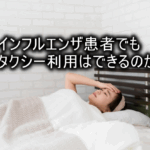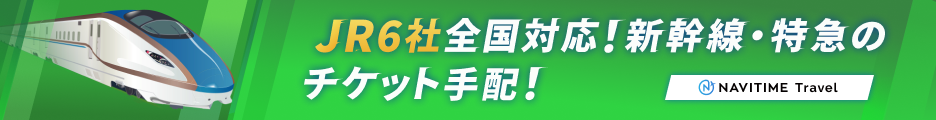「救急車」というワードを聞くと、誰しもが119番に電話するとすぐに駆け付け病院まで搬送してくれる「消防救急」を思い浮かべます。
しかし、救急にはもう一つの「救急車」があるのです。
それが「民間救急」です。
聞いたことある。利用したことはないが存在は知っている。…という方もいらっしゃるでしょう。
ですが、「お金を払えば、具合の悪い人を運んでくれる。」といった認識が大半です。
その業務内容や利用方法などについて、詳しく知っている方は多くありません。
そこで当記事では、ふたつの救急車についてその違いや共通点などを「民間救急」に焦点を当てながら解説していきます。
ふたつの救急車の共通点
そもそも「民間救急」とは、緊急性の低い傷病者を搬送してくれる民間事業者のことで、事業そのものや提供サービス、使用車両などにも包括して使われています。
「民間救急」の正式名称は、消防庁の指導基準に基づくと「民間患者等搬送事業」となります。
この民間救急と区別するため、119番の救急車を「消防救急」と呼んだりもします。
ただ、一般的に「救急車」というと「消防救急」を指し示します。
あまりにもメジャーすぎるので、仕方ありませんね(笑)
では、「民間救急」と「消防救急」…この二つの救急車の違いを解説する前に、共通点を整理しておきましょう。
- 傷病者の搬送
- 医療に関する専門知識を有した人員
- 医療機関との連携
上記が主な共通点です。
なかでも最大の特徴は、どちらもの救急車もケガや病気の人…傷病者を搬送するという目的を担っていることです。
そのためには、傷病者の状態を的確に把握し、搬送中は症状を維持する必要があります。
そのため、どちらの救急車も医療の専門知識を有した人員が配置されています。
もちろん、搬送元や搬送先になる医療機関とも連携を取り合う必要があります。
実際に搬送したのに、病院が受け入れてくれない…では話になりませんからね。
どちらの救急車も、事前に連絡し受け入れの了承をもらってから搬送しています。
もっとも、消防救急はその性質上、「事前」が搬送の「直前」になってしまうのは致し方ありません。

消防救急にできること
消防救急の最大の特徴は「緊急性が高い傷病者を医療機関まで搬送すること」です。
そのため、民間救急ではできないことが、消防救急には許可されています。
大きな内容は下記の二つです。
- 緊急走行および赤色灯やサイレンの装備
- 医療行為
1.緊急走行および赤色灯やサイレンの装備
傷病者の緊急性が高いため、いち早く医療機関へ搬送しなければなりません。
そのような事情から、消防救急には「緊急走行」が許可され、道路の優先通行権が与えられています。
具体的には、赤信号交差点への侵入や一時停止の免除、対向車線の通行などが可能となります。
一般車両は緊急車両が近づいてきた際には、道路左側に車体を寄せ、進路を譲らねばなりません。
ただし、緊急走行が許可されるのは一定の条件を満たした時だけです。
例えば、赤色灯や前照灯の点灯、サイレンの吹聴などが緊急走行の要件となっています。
残念ながら、民間救急には緊急走行の要件を満たすための赤色灯やサイレンなどを装備することはできません。
2.医療行為
また、消防救急では医療行為も認められており、救急救命士は医師の指示のもとであれば、特定行為と呼ばれる医療行為を行うことが可能です。
具体的には気管挿管や静脈路確保、エピネフリンなどの薬剤投与がそれにあたります。
さらには、血糖の測定やブドウ糖の投与など、救命士が行える医療行為は近年拡大されています。
今後もアナフィラキシーショックに対するエピペンの使用など、その他の医療行為も拡大されていくことでしょう。
本来なら、医療行為は医師しか行えません。
しかし、特定されているとはいえ、これらの医療行為が認められるのも、消防救急が緊急性の高い傷病者を搬送しているためといえるでしょう。
これらの医療行為は医師の指示のもと、プロトコルとよばれる厳格な手順書に沿って行われています。
さらには、実際に行う救急救命士も多くの教養と訓練を経て国家資格を取得し、病院での実習を繰り返し行っています。
救急車での医療行為を心配する必要はありません。

民間救急にできること
消防救急にしかできないことがあるからと言って、消防救急が偉いわけではありません。
反対に民間救急にしかできないこともあります。
それが下記の二つになります。
- 個人での予約
- 有償による緊急性の低い傷病者の搬送
1.個人での予約
民間救急は個人で予約することが可能です。
「〇月×日の10時に自宅へ来て、再入院先の病院まで搬送して欲しい。」というような利用をすることができます。
そもそも民間救急の利用には事前予約が必要です。
実務的にも人員の確保や車両の整備もしなければなりませんし、搬送先への連絡などの手配も必要になるからです。
反対に、消防救急では個人による搬送の予約は出来ません。
なぜなら、「予約」という時点で「緊急ではない」ですから。
例外的に手術などの理由による転院搬送など、医療機関からの予約は消防救急でも取り扱いうことがあります。
2.有償による緊急性の低い傷病者の搬送
そしてなにより「緊急性の低い傷病者の搬送」こそ、業務目的であり、本来民間救急にしかできないことといえます。
そもそも消防救急は緊急性の高い傷病者の搬送を任務とし、それ以外の傷病者は本来搬送できないのです。
みんなの税金で行われるため仕方ありません。
ですが、緊急性が低くても搬送を希望する傷病者や家族は確実に存在します。
高齢などで体が衰弱して座った状態で移動できない。
病気やケガなどのため、家族の力のみでは外出は不可能。
…などといった方々は多くいます。
その方々の助けとなるのが「民間救急」なのです。
利用料金はかかりますが、その分様々な面で融通が利きます。
例えば「寝たきりで入居中の福祉施設から、実家へ里帰りさせて欲しい。」などといった、医療機関以外への搬送も行っています。
また、いくつもの県をまたぐような遠方への搬送も問題ありません。
さらには搬送時間以外でも、待機してもらうことも可能です。
つまり、通院や入退院だけでなく、思い出作りの旅行や冠婚葬祭などのイベントへの出席などにも利用することができます。

まとめ~民間救急を有効活用しよう
民間救急は「緊急性の低い傷病者の搬送」が業務目的です。
消防救急では手を差し伸べられない方々への必要なサービスであり、少なくない需要があるでしょう。
そして高齢化の進む日本社会において、さらに需要は伸びていくと考えられます。
さらに融通の利かない消防救急とは異なり、搬送先や使用目的に縛られることもありません。
予約し料金さえ払えば、医療機関だけでなく、個人的なイベントへの移動手段として活用することができます。
また、消防救急の不適切利用が問題となる中、民間救急の利用が徐々にクローズアップされるようになってきています。
緊急性の低い傷病者が民間救急を利用することにより、消防救急が緊急性の高い事案のみに集中することができます。
これは消防救急のみならず、救急医療のひっ迫を防ぎ、全体により良い効果をもたらすでしょう。

つまり民間救急は、個人には「融通の利く移動手段」として役立ちます。
その上、社会的には「消防救急の負担を減らし、救急医療のひっ迫を防ぐ手段」としても有効なのです。
これから消防救急の有料化(正確には病院での選定療養費の徴収)が進めば、適正利用の観点から、さらに民間救急の利用が促進されるでしょう。
二つの救急車のできることできないことに着目し、民間救急を有効活用しましょう!!
この記事が、民間救急の利用の一助となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。