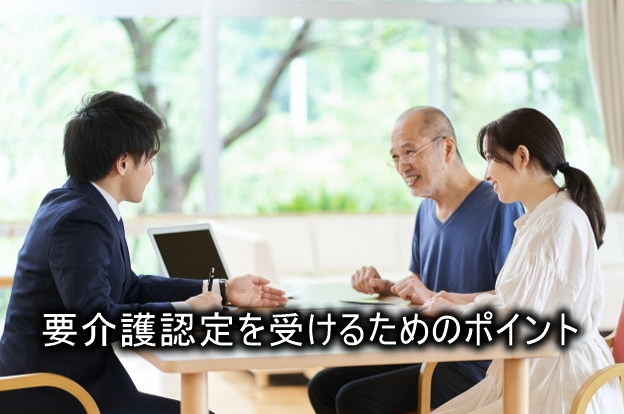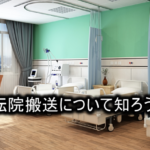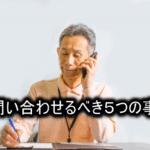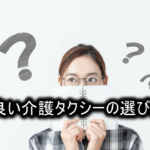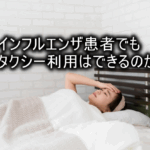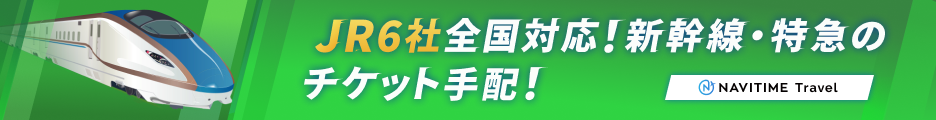病気後に引きこもり気味なってしまった親を、ディサービスに通わせたい。
仕事の都合もあるし、在宅での介護も厳しい。
このように家族が介護が必要な状態になってしまうと、労力も費用もかかるため大きな負担となります。
そんな時に強い味方になってくれるのが「介護保険」です。
例えば介護保険では、在宅介護で受けられる「居宅サービス」や施設に入居する「施設サービス」などを受けることができます。
これにより、身体的にも金銭的にも負担が大幅に軽減されることは間違いないでしょう。
ただしこの「介護保険」は、誰しもが利用できるわけではありません。
そこで当記事では、介護保険を利用するために必要な「要介護認定」について、認定を受けるポイントを踏まえて解説していきたいと思います。
介護保険を利用には要介護認定が必要
介護保険とは、介護が必要な方にその費用を給付してくれる公的な社会保険になります。
保険の一種ですから皆で費用を負担し、必要な方へ給付する仕組みです。
この給付を受けるには手続きと審査が必要になります。
皆さんの大切なお金を、一部の方々に分配するわけですから当然ですね。
その給付が「必要な方」というのが、「要介護認定を受けた方」になります。
要介護の認定を受けなければ、費用の給付はありませんし、公的な各種の介護サービスを利用することも出来ません。
つまり、自身や家族に介護が必要になったら、急いで要介護認定を受ける必要がある、という事を覚えておきましょう。
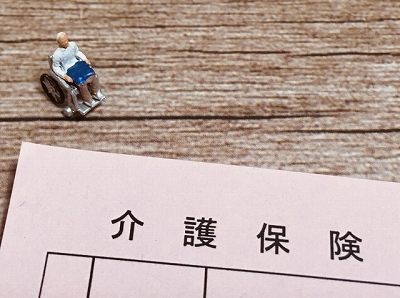
要介護認定の流れ
要介護認定を受けるためには、下に記した一連の手続きが必要です。
- 申請
- 訪問調査
- 主治医の意見書
- 一次判定&二次判定
- 結果通知
1.申請
要介護認定を受けるためには、市区町村の高齢者を担当する福祉課の窓口に申請する必要があります。
なお、入院等で本人が申請できない場合は、家族が代理で申請することも可能です。
また代理申請や手順等に不安があれば、地域包括支援センターに前もって相談しておくと良いでしょう。
2.訪問調査
申請が受け付けられると、日程調整の上、訪問調査が行われます。
調査は市区町村の職員や委託されたケアマネージャーが、実際に利用者の住まいを訪問し生活や心身の状況、特別な医療の必要性などを調査します。

調査項目は以下の6つに大別されます。
- 身体機能・起居動作
- 生活機能
- 認知機能
- 精神・行動障害
- 社会生活への適用
- 特別な医療に関する項目
これらに関する所定の質問票を用いて、調査員がチェックする形式で行われます。
なお、質問票は全国共通となっています。
もちろん、質問票に沿っているだけでは実態が把握できない場合もおおく、特記事項の記載欄があります。
3.主治医の意見書
また、訪問調査と並行して、主治医に意見書を提出してもらう必要があります。
この意見書には、利用者の病気の状態などを医学的見地からみた意見がまとめられています。
かかりつけ医がいない場合は、市区町村の担当窓口や地域包括支援センターで相談してください。
職員と相談してかかりつけ医を決め、診察を受けた後に意見書を作成してもらう事になります。
4.一次判定&二次判定
訪問調査の質問票と主治医の意見書の内容をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
そして「一次判定の結果」と「主治医の意見書」「質問票の特記事項」を基にして、二次判定となる介護認定審査会が開かれます。
審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5名ほどで構成され、要介護度の判定を行います。

5.結果通知
申請から結果の通知までは通常30日程度の日数がかかります。
ただし、訪問調査の日程や意見書の提出が遅れると、当然後ろ倒しになることも少なくありません。
地域によっては2カ月程度かかる場合もあります。
申請する時にはすでに介護を必要としている状況でしょうから、要介護認定に関する手続きは急いで行ってしまいましょう。
認定のためのポイント
要介護認定の申請をしたものの認定がもらえなかったり、希望より要介護度が低かったり、というケースも多くあります。
このような結果にならないよう注意すべきポイントには、下記のようなものがあります。
- 事前にかかりつけ医を決めておく
- かかりつけ医に家族の要望を伝えておく
- 訪問調査には必ず立ち合う
- 調査員に伝えることをリストアップしておく
- 必要な要介護度(介護サービス)を論理的に伝える
1.事前にかかりつけ医を決めておく
かかりつけ医を事前に決めておくメリットは二つあります。
一つ目は申請から結果通知まで、余計な日数がかからないようにするためです。
かかりつけ医を決めておかないと、前述の通り申請してからかかりつけ医を探す必要があります。
そのため、その分余計な日数がかかってしまいますね。
介護は待ってくれません。
事前にかかりつけ医を決めておきましょう。
二つ目はかかりつけ医を決めておくと、医師にこちらの状態を前もって知ってもらうことが出来ます。
さらに、こちらも医師の人となりを知っておくことが出来るでしょう。

2.かかりつけ医に家族の要望を伝えておく
また、かかりつけ医を決めておくと意見書を書いてもらう際に、家族からの要望を伝えやすくなります。
「主治医の意見書」は審査会で重視され、判定に大きな影響を及ぼします。
そのため、こちらの事情をよく理解し親身になってくれる医師に意見書を書いてもらう事が大切になります。
意見書を依頼する際には、改めてこちらの要望を伝えておくと良いでしょう。
例えば「現在家族が苦労している点」「使いたい介護サービス」「受けられなくなると困る介護サービス」など、まとめておきましょう。
できれば、手紙などの形にして渡した方が、医師も意見書を作成しやすくなります。
3.訪問調査には必ず立ち合う
訪問調査に家族の立会いは必須ではありません。
しかし、訪問調査には家族も必ず立ち合いましょう。
というのも、利用者は往々にして見栄を張りたがるものだからです。
「出来ないこと」を「出来る」と答えたり、「困っていること」を「問題ない」と言ったりしがちです。
利用者本人の「恥ずかしい」という気持ちが、そう答えさせることは理解できます。
しかし、それで正しい要介護認定がもらえないのは、本人も家族も困るのです。
現状を正しく伝えるためにも家族は必ず立会いましょう。
4.調査員に伝えることをリストアップしておく
また、訪問調査前には「事前準備」をしておきましょう。
特に初めての訪問調査の時は段取りもわからず、調査員の質問だけに答えて終わってしまう…などという事も考えられます。
それだけでは自分たちが何に困っていて、何を必要としているのかが伝わるはずもありません。
そのため、訪問調査が決まったら、伝えるべきことをリストアップしておきましょう。
「これだけは!」と思えるものをメモにまとめて、当日に挑みましょう。

5.必要な要介護度(介護サービス)を論理的に伝える
また、調査時には「必要としている介護サービス」を伝えましょう。
その際「現在困っていること」と「その問題解消ために必要な介護サービスとその回数」を論理だてて説明することで、調査員の理解も深まるでしょう。
また、そこから必要な要介護度も導き出されます。
ただ「手厚い給付が欲しい」「これ以上、金銭的な負担を増やせない」というだけでは、調査員を納得させることは出来ません。
理屈が通っていれば、特記事項に記載してもらえる可能性も高くなり、審査会で有利に働くでしょう。
移動に困ったら介護タクシー
晴れて審査を通り、要介護認定の結果通知を受け取ったらケアマネージャーを紹介してもらい、ケアプランを作成することになります。
その際、外出などの移動に不自由を感じていたり、家族の送迎が期待できない場合は「介護タクシー」の利用を検討しましょう。
介護保険を使用すれば、介護料金部分が1割負担となり、通常より安く介護タクシーを使用することが出来ます。
通院などの送迎を介護タクシーで行えば、家族は負担も減るうえ、時間的な余裕も生まれます。
介護はゴールのないマラソンの様なもの。
いつまで続くか分かりません。
そのため、介護サービスを利用し日々の負担をいかに減らせるかが、介護生活を良好に乗り切る秘訣です。
介護タクシーを適切に利用して、介護生活に余裕を持たせましょう。

~まとめ~
要介護認定を受ける、または希望の要介護度を受けるためには、こちらの現状を正しく理解してもらう事が大切です。
何に困っていて、どのような介護サービスをどのくらいの回数必要としているのか?
これらを論理的に訪問調査員に伝えることが重要になります。
また、かかりつけ医にも要望を伝え、意見書で後押ししてもらえるよう、働きかけましょう。
要介護認定は一度で終わりではありません。
有効期限があり、更新には再度訪問調査と審査会が開かれます。
介護生活が続く限り年1回は行われます。
希望の要介護認定を受けられるよう、しっかりとポイントを押さえておきましょう。
この記事が要介護認定審査の一助となれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。